サステナビリティSustainable
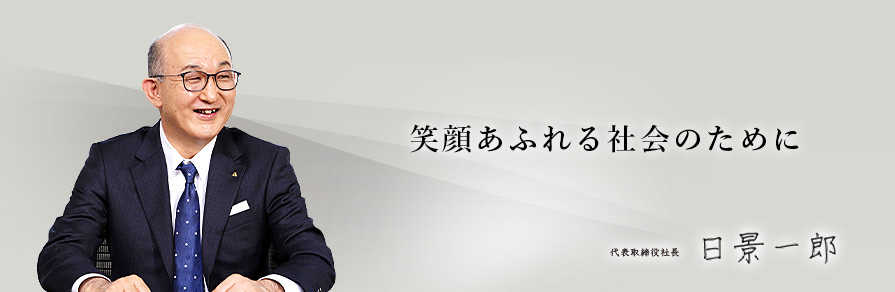
2022年度は、原材料価格、エネルギーコストや物流費などが過去にないレベルで高騰し、当社の業績に大きく影響を及ぼしました。コストダウンや物量増、新製品投入などの努力を重ねましたが、コスト上昇を吸収するには及ばず、お客様との対話を重ね、価格改定を実施させていただきました。
しかしながら、コスト上昇分全てを吸収するには至らず、2022年度の連結ベースでの営業利益は△713百万円、経常利益は△117百万円、当期純利益は△1,204百万円となりました。当期純利益を押し下げた主な要因は、断熱資材事業ならびに床材事業の減損処理によるものです。両事業に関しましては、損益分岐点を引き下げる観点からのコスト低減に加えて、新製品開発を推進するとともに、引き続き価格改定にも取り組みます。また、今年度もコストの高止まりが見込まれることから、他事業におきましても、引き続き自社の努力と価格改定を継続推進するとともに、お客様の困りごと解決や歩留まりの改善につながる価値の提案、サービスの向上などに積極的に取り組んでまいります。
また、コスト高以外にも、変化が激しい経営環境に適宜適切に対処していく必要があります。ステークホルダーの皆様には、引き続き当社に対しましてご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2019年に、車両・航空機用内装材の製造・販売子会社として中国広東省佛山市に設立した阿基里斯(佛山)新型材料有限公司は、新型コロナウイルス感染症の影響で設備導入が当初計画より遅延しておりましたが、ようやく完了し、2022年12月に開所式を行いました。今期は、本格的に量産が行えるよう、スペックイン活動をさらに推進してまいります。また、中国国内では、EV車が急速に普及していることから、阿基里斯(佛山)製品の特長を生かし、EV車向けにもマーケティングを強化しています。
国内製造拠点では、軟質ウレタンフォームを製造する工場で発泡設備や加工設備を増強しております。さらには、研究開発用の発泡設備も導入しており、これらにより品質と生産性の向上を図るとともに、新製品開発にも注力してまいります。投資案件に関しては、確実に投資回収を図るべく、全社一丸となって取り組んでまいります。
当社は、今年4月にTCFD※提言への賛同を表明し、気候変動が当社事業に与える影響について、2℃未満シナリオと4℃シナリオを用いてリスクと機会の分析を行いました。2℃未満シナリオにおいては、日本に炭素税が導入された場合には財務的インパクトが大きくなる一方で、当社事業をソリューションとして活用できる機会を確認しています。また、4℃シナリオにおいては、水害による被災リスクの影響を確認しましたので、適切に対処していきます。
当社は、政府方針である「2050年カーボンニュートラル実現」のビジョンを共有しつつ、温室効果ガス排出量(スコープ1・2)を、2030年までに2018年度比30%削減することを目標としています。具体的な取り組みとしては、省エネの徹底、コジェネ設備の導入、再生可能エネルギーの調達、太陽光発電の自家消費、クレジット購入などに加え、今後新たに普及する技術などを総合的に勘案し、当社にとっての最適化を図っていきます。
また、今後は、温室効果ガス排出量のスコープ3の把握や、海外拠点を含む子会社における温室効果ガス排出量の削減に取り組んでまいります。
当社は、プラスチック加工をコアとし、グローバルに事業を展開しています。配合技術力、加工技術力、設備設計力、情報処理技術力、新製品開発力などの知的財産を創造する能力に加え、ユニークな販売戦略、財務・会計能力などの企業経営力、「語学力」に加え海外に通用するビジネススキルなど海外展開を推進していく上で必要な能力などを高め、それぞれの分野で当社の柱となる従業員を育成・活用することが、当社の持続的な成長には欠かせません。そのため、これら多様な人材を育成・活用する上での基本方針を定めています。根本にある考え方は、「多様な人材が持つ多様な価値観、個性のコミュニケーションがイノベーションの創出につながる」というものであり、従業員一人ひとりが意欲や能力を十分に発揮することができる企業文化の醸成を目指しています。多様性を醸成する上での一つの視点として、管理職への女性の登用は必要不可欠ですが、その前段の取り組みとして、女性の雇用率を一定以上確保することや、各種研修など能力開発の機会は性別の区分なく提供し、業務に必要なスキルの習得や能力開発を支援しています。
また、専門的なスキルや経験を必要とする業務に対応するため、経験者(中途採用者)を積極的に採用し、管理職に登用しています。
アキレスグループにとって、従業員は最大の財産であり、従業員の成長は、当社グループが持続的な発展を遂げるために欠くことができないものと捉えています。
現在の当社事業のポートフォリオを売上高で見ると、シューズ事業13.7%、プラスチック事業50.9%、産業資材事業35.4%となっています。
シューズ事業は、早急に事業の黒字化が必要であり、カテゴリーの選択と集中を進めます。マーケットのセグメントごとにあらためて精緻なマーケティングを行い、注力すべきセグメントに集中いたします。また、WEBシステムを活用して一層営業効率を高めることや、為替の影響を受けにくい東アジアへの拡販に努めるなど収益性の早期改善に取り組んでまいります。
プラスチック事業は、コロナ禍などの影響で自動車関連の事業で販売の停滞があったものの、2023年度は回復を見込んでいる一方で、高止まりしているコストをいかに吸収するかが課題です。また、2021年度に設置した防災事業部の事業規模を拡大させることが目下の重点事項と位置づけています。この防災事業は、多様な製品製造技術を有している当社の強みを生かせるものであり、新たに立ち上げた防災工場を拠点として、救助用ボートや防災用のエアーテントに加え、公助から自助・共助となる地域住民向け製品や法人向けの帰宅困難者支援製品など、当社の総合力を生かした新製品開発も加速させ、販売拡大を図ってまいります。
産業資材事業は、喫緊の課題として採算が悪化している断熱資材事業の収益性を改善せねばなりませんが、この事業は、レベルの高い省エネルギー住宅の普及に貢献できるものであり、事業戦略の柱の一つに位置づけております。また、静電気対策製品を扱う工業資材事業においては、新たに各地で半導体製造拠点が建設されることから、販売機会と捉え、マーケティングを強化しています。
また、海外の事業においても、米国ではアキレスUSAにおいて医療用フィルムの製造設備を増強することを予定しており、中国の阿基里斯(佛山)も含め、海外事業の拡大推進を図ってまいります。また、既存・新設の海外の製造・販売拠点を生かし新規分野にも挑戦していく所存です。
以上の通り、現状、各事業の収益性改善が喫緊の課題でありますが、中長期的な観点では、当社のセグメントフィールドが広い分、成長の機会も多く点在していることから、適時適切な投資を行うことで課題解決を図り、成長につなげていけると考えています。
当社の製品・サービスがお客様の困りごとや社会的課題を解決することで、笑顔が少しずつ増え、やがて社会にあふれることを目指したいと思っています。そのためにも、グループの全従業員がお互いを尊重し、皆が使命感を持って笑顔で業務に取り組む企業文化を醸成し、安心で安全な職場環境づくりを推進いたします。
アキレスグループは、「社会との共生=顧客起点」の企業理念のもと、「笑顔あふれる社会」を実現すべく、全社一丸となって邁進してまいります。
2023年9月